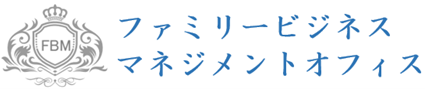行政書士法が改正~補助金や経営革新計画の支援を受ける際に気をつけたいこと

補助金や経営革新計画を活用するには、事業計画書の質がカギとなります。2025年に改正され、2026年に施行される行政書士法では、「作成業務」の定義や資格要件がより明確に。本記事では、相談(助言・支援)業務と「作成」業務の違いや、支援を依頼する際の注意点、専門家選びのポイントを丁寧に解説します。
補助金や経営革新計画、計画書の完成度がカギになります
補助金や経営革新計画は、事業の成長や変革に向けた一歩として、有効に活用できる制度です。
一方で、申請にあたって必要となる事業計画書の作成にハードルを感じる方も少なくないかもしれません。
「自社の強みをどう書けばいいのか分からない」「時間がとれず手がつけられない」
そうしたお悩みは、多くの事業者の方に共通するものです。
そのような中で、専門家の力を借りることは有効な選択肢といえます。
ただし、誰に、どのように支援をお願いするかには一定の注意が必要です。
行政書士法の改正のポイント(2026年1月施行予定)
行政書士法が2025年6月に改正され、2026年1月1日から施行されます。
今回の改正では、行政書士の「使命」や「職責」が明文化されるとともに、
書類作成業務における報酬の名目や形式を問わず、無資格での作成を禁ずる規定が明確になりました。
行政書士の「使命」「職責」の明文化
国民の権利利益の実現に資することや、デジタル社会への対応努力など、これまで実質的に求められていた姿勢が条文上にも明示されました。
特定行政書士の業務範囲の拡大
申請代理に加えて、不服申立てまで一貫して対応できるよう、条件の緩和が図られました。具体的には、不服申立てについて、行政書士が「作成した」ものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されました。
書類作成業務に関する規定の整理
行政書士でない者が「作成」業務を行うことに対し、「いかなる名目であっても報酬を得て行えば違法となる可能性がある」ことが明確にされました。
両罰規定の整備
行政書士法人などについて、違反があった場合に法人にも責任が問われる規定が追加されています。
これらの改正は、行政手続きの透明性や信頼性をより高める方向でなされたものと受け止められています。
支援を受ける際に、確認しておきたいこと
専門家にサポートをお願いする際には、「支援の範囲」がどこまでかを確認しておくと安心です。
助言や相談は問題にならないケースが多いです
たとえば、構成のアドバイスや、事業内容の整理方法、採択されやすい書き方の方向性などについて、
口頭やコメント機能を通じてアドバイスをもらうといった支援は、法令上も一般的に認められています。
事業計画書そのものを整えてもらう場合は注意が必要です
たとえば、以下のような行為は、行政書士法上の「作成」にあたる可能性があるとされています。
- 申請様式の空欄に代わって記入してもらう
- WordやPDFファイルに直接赤入れ(修正)をしてもらう
- そのまま提出できる完成原稿を第三者に整えてもらう
こうした行為を、報酬を得て反復継続して行う場合には、行政書士資格が求められるとされており、たとえ「顧問料」や「コンサルティング費」など他の名目で報酬を受け取ったとしても、注意が必要です。
また、報酬が発生しない場合でも、内容や態様によっては同様の扱いになることがあるとされています。
事業計画書の作成支援が「作成」に該当する判断基準(目安)
※横にスクロールできます。
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 書類そのものに手を加えたか | 申請者のファイルに直接文章を入力・修正・追記した場合は「作成」 |
| 完成版として渡したか | 「そのまま提出可能な内容の文書」を納品した場合も「作成」 |
| 修正指示か、編集行為か | コメント・助言は「相談」だが、書き換えて返却するなら「作成」 |
「作成」に該当しないとされる行為(合法な助言)
※横にスクロールできます。
| 行為 | 該当しない理由 |
|---|---|
| 書き方の一般的助言(構成・表現・文体) | 「相談」(第1条の3)に該当 |
| コメント機能で「この表現を見直すと良い」と助言 | 申請者が修正する前提だから |
| 公募要領の読み方や採択ポイントの解説 | 書類作成にあたらない知識提供 |
自分で作る+専門家の支援を受ける、という考え方
補助金や経営革新計画などの申請は、単なる書類作成の作業ととらえるのではなく、自社の経営の方向性や今後の戦略を見つめ直す貴重な機会とも言えるでしょう。
日々の業務に追われていると、あらためて「自社は何のためにこの事業を行い、今後どう成長していくのか」を考える時間はなかなか取れないものです。だからこそ、申請書の作成をきっかけに、自社の強みや課題、将来像について整理するプロセスには大きな価値があります。
そのためにも、「誰かに任せきりにする」のではなく、まずは自分で考え、書いてみるという姿勢を持つことが大切ではないでしょうか。
そのうえで、専門家の支援を受けることは、方向性の整理や表現の工夫などを通じて、その取り組みをより深めていくための後押しになります。
私たちが担うのは、答えを代わりに書くことではなく、経営者自身が納得し、自信を持って語れる事業計画をつくるための伴走者としての役割だと考えています。
おわりに:信頼できる支援者と、安心して取り組むために
補助金や経営革新計画に関する支援は、制度や法令に精通した専門家に相談することで、
より安心して進められる場合が多いように思います。
支援をお願いする際には、支援者の資格や役割、支援範囲についてあらかじめ確認しておくことが、
結果的にお互いにとって良い信頼関係にもつながります。
行政書士・中小企業診断士・認定支援機関など、それぞれの専門性を活かしながら、
事業のステージや目的に応じた支援体制を活用していただければと思います。
【参考】
・「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について(日本行政書士連合会)
・行政書士制度(総務省)
ご相談は「平野経営法務事務所」へ
補助金申請や経営革新計画の作成にあたり、
「制度の活用方法がわからない」「計画書の作り方に不安がある」
そんなお悩みはありませんか?
平野経営法務事務所では、行政書士・中小企業診断士・認定支援機関の資格を有する専門家が、
事業者の想いをかたちにする計画づくりを、責任をもって丁寧にサポートいたします。
私たちが大切にしているのは、
- 計画書の“代行”ではなく、“納得しながら自分で書けるようになる”プロセス支援
- 単発の申請だけでなく、次の成長や資金調達につながる計画づくり
- 法令をふまえた安心の支援体制と、継続的な伴走支援
たとえば、こんな方におすすめです
- 補助金申請にあたり、採択率を高める計画の立て方を知りたい方
- 経営革新等支援機関の認定制度を資金調達や信頼性向上に活かしたい方
- これまで「書いてもらっていた」申請書を、今後は自分で書けるようになりたい方
- 顧問税理士やコンサルとは違う視点から、公的支援制度の正しい活用法を知りたい方
ご相談は初回無料です。
「制度の活用に興味がある」「何から始めればいいかわからない」といった段階でもお気軽にどうぞ。
— あなたの挑戦に、正しく・ともに寄り添う支援を。
平野経営法務事務所が、次の一歩をサポートします。—
ファミリービジネスマネジメントオフィス
行政書士平野経営法務事務所
代表・行政書士 平野 泰嗣