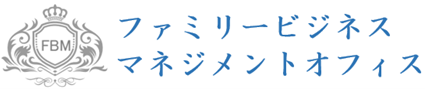【第1回】家族と企業、両輪で進む経営とは:家業経営に活きる“並行思考”のすすめ

~家族の想いと企業戦略をつなぐ実践アプローチ~
ファミリービジネスは、事業と家族という二重構造を抱えた経営形態です。本記事では、その複雑さに応える考え方として注目される「パラレルプランニング」について、6つの領域に整理しながら解説。日本の家業文化との親和性や、事業承継の現場での課題、感情と仕組みの調和のヒントも紹介しています。
ファミリービジネスに求められる二重構造へのまなざし
企業経営には通常、事業の成長や組織の効率化といったビジネスの視点が求められます。しかし、ファミリービジネスにおいては、それだけでは語りきれないもう一つの側面――「家族」が関与するという特性があります。経営と家族。両者が密接に絡み合いながら、時に補完し合い、時に衝突する。こうした二重構造の中で、経営判断をどう導いていくかは、ファミリービジネスにとって極めて重要なテーマです。
その複雑さに応える考え方が「パラレルプランニング」です。本記事では、このパラレルプランニングの基本視座と、日本の家業文化における実践の可能性について解説してまいります。
「ファミリー」と「ビジネス」――ふたつの時間軸と意思決定の構造
ファミリービジネスの経営者であれば、日々の経営判断において、「ビジネスとしての正解」と「家族としての納得」の間で揺れることがあるのではないでしょうか。例えば、業績向上のために外部の専門経営者を招聘したいと考えても、親族の期待や社内の空気がそれを難しくする。あるいは、兄弟姉妹に経営権をどのように分けるかという問題に、感情的な葛藤が絡むこともあります。
こうした課題の背景には、「ビジネス」と「ファミリー」という二つの異なる時間軸と意思決定のロジックがあります。
- ビジネスの時間軸は、市場や競合、顧客の動向をにらみながら、スピーディに合理的な判断を求められるものです。短期的成果を重視し、効率性が優先されます。
- 一方で、ファミリーの時間軸は、長期的で情緒的な関係性に根差しています。親子三代、あるいは兄弟姉妹の絆や家訓、祖業への想いといった、目に見えない要素が大きく影響します。
この二つの軸が同時に存在するのが、ファミリービジネスの特徴です。どちらか一方だけを優先すれば、もう一方が傷つくこともあります。そこで必要になるのが、「両方の視点を並行して計画する」=パラレルプランニングの考え方です。
パラレルプランニングとは?――海外理論と日本の家業文化
「パラレルプランニング(Parallel Planning)」は、ハーバード・ビジネス・スクールのファミリービジネス研究で知られるジョン・デイヴィス教授らによって提唱された概念です。この考え方は、以下の6つの領域において、「ファミリー」と「ビジネス」の両方の視点から計画を立てる必要があると説いています。
※横にスクロールできます。
| 領域 | ファミリーの視点 | ビジネスの視点 |
|---|---|---|
| 資産計画(Capital) | 家族資産の保全・相続 | 事業資本の確保・投資戦略 |
| 所有計画(Ownership) | 株の継承、家族内の公平性 | 株主構成の安定、経営支配の確保 |
| 経営計画(Management) | 家族の関与とキャリア | 専門性・外部人材の活用 |
| リーダーシップ計画(Leadership) | 誰が家族の代表か | 経営者の選任と育成 |
| 継承計画(Succession) | 家族の承継意向 | 経営と所有のスムーズな移行 |
| 文化と価値観(Culture & Values) | 家族の信念や伝統の継承 | 企業文化・ビジョンとの整合性 |
これらの領域において、家族の思いや背景を汲み取りながらも、経営としての合理性や持続性を確保していく。それがパラレルプランニングの目的です。
たとえば、「所有計画」では、誰にどのように株式を譲るのかという家族内の公平性の配慮が求められる一方で、経営上は議決権や支配権を安定させる必要があります。また「継承計画」においても、単に事業を引き継ぐだけでなく、家族内の意志をどう整えるかが問われます。
日本における「家業」や「暖簾(のれん)」の文化も、実はこのパラレルプランニング的な考え方に近いものがあります。古くからの家訓や「長男が継ぐ」という不文律などは、暗黙のうちにファミリー側の論理とビジネス側の実利を接続しようとしてきたとも言えます。ただし、それらは制度化されていなかったために、現代の多様化する家族像やキャリア観には対応しきれなくなってきています。
だからこそ今、こうした「並行思考」を形式知として可視化し、計画として整理することが求められています。
なぜ今、必要とされているのか?――承継の現場で起きていること
現在、日本のファミリービジネスの多くが、承継の転換期にあります。中小企業庁のデータでも、多くの中小企業経営者が70代に入り、後継者不在や承継未定が大きな課題となっています。
しかし、単に「後継者を決めておく」だけでは不十分です。実際には、次のような問題が頻発しています。
- 経営者が交代しても、株式は前経営者が握り続け、意思決定が二重構造になる
- 家族の中で誰が継ぐかの合意が得られず、感情的対立を引き起こす
- 後継者は決まったが、現場を知らずに経営が迷走する
- 承継の意向を示すタイミングを逸し、事業売却や廃業に追い込まれる
これらの失敗には、共通して「家族と経営を並行して設計していなかった」という背景があります。感情と利害の調整を後回しにした結果、機を逸するのです。
パラレルプランニングを実践することにより、こうしたリスクをあらかじめ把握し、備えることが可能になります。特に、早い段階からの対話と役割整理は、承継をスムーズにする土台となります。
感情と仕組みの調和をどう設計するか?
ファミリービジネスにおいては、経営のあらゆる場面で「感情」が入り込むのが自然なことです。しかしそれを“排除”するのではなく、“前提として受け入れ、設計に組み込む”ことが、パラレルプランニングの鍵となります。
たとえば、次のような仕組みが効果的です。
- ファミリー会議の定期開催:家族間で自由に意見を交わし、方針や役割を共有する機会
- ファミリー憲章の作成:家族としての価値観やルール、事業に対する考え方を文章化
- 社内での役割分担の明確化:親族内での職務・権限を明示し、組織内の混乱を防止
- 経営と家族の相談窓口の分離:ガバナンス体制として、取締役会や顧問を活用
感情を適切に吐露できる場を用意しつつ、企業としての意思決定には透明性と客観性を保つ。そうした“バランス設計”こそが、ファミリービジネスの永続に不可欠です。
おわりに――次世代に引き継ぐための「土壌づくり」
パラレルプランニングは、単なる承継対策や資産管理ではありません。それは、家族と経営がともに成長するための“共創の設計図”であり、次世代に「継ぎたい」と思ってもらえる環境を整えることに他なりません。
次回は、6領域の中でも特に実務上の悩みが多い「所有と資産」のテーマを取り上げます。株式の分配やガバナンスと、家族の想いをどうバランスさせるか。その実践的なヒントをお届けします。
ファミリービジネスマネジメントオフィス
シニア・プライベートバンカー
平野 泰嗣
<ご留意事項>
本記事は、ファミリービジネスにおける経営・所有・資産承継・ガバナンスに関する一般的な情報を提供するものであり、特定の企業や個人への経営判断、投資判断、法的助言、税務助言を行うものではありません。株式の承継、資産分与、ファミリー憲章や会議体の設計などは、企業ごと・家族ごとに事情が異なります。実際の計画や制度設計を行う際は、必ず弁護士、公認会計士、税理士、プライベートバンカーなどの専門家にご相談ください。なお、記事内容は執筆時点の法令・制度等に基づいており、将来予告なく変更される場合があります。
ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMオフィス)からのご案内:
「うちの会社にも当てはまるかも…」そう感じた方へ。
ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)では、家族と企業の未来を大切にした、あなただけの経営支援を行っています。
小さな疑問から、複雑な承継の悩みまで、お気軽にご相談ください。
経験豊富なアドバイザーが、じっくりお話をうかがいます。
👉 お問合せ・初回相談のご予約はこちら