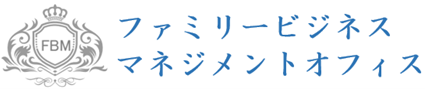ファミリービジネスの持続可能性とリスク管理:不測の事態に備える経営戦略

~ファミリービジネスを揺るがすリスクに、今からどう備えるか?~
ファミリービジネスにおける経営リスクは、経営者依存、家族間の対立、情報の属人化など、表面化しづらく対処が遅れがちなものばかりです。本記事では、そうした“見えないリスク”にどう備えるべきかを体系的に解説。経営の「見える化」、ファミリーガバナンス、事業継続計画(BCP)の整備など、実践的な対応策を紹介します。企業の持続可能性を高めるためのリスクマネジメントの考え方と、今日からできる点検ポイントをまとめました。
ファミリービジネスに今リスクマネジメントが必要な理由とは?
ファミリービジネスは、血縁による強固な絆や、長年にわたる地域・取引先との信頼関係、トップダウンによる迅速な意思決定を強みに、安定感のある経営を続けている企業が少なくありません。経営基盤が地に足ついており、特別なトラブルがない限り、日々の運営は順調に見えることが多いものです。
しかしその一方で、「これまで問題が起きなかったから、これからも大丈夫だろう」という油断や過信が生まれやすいのも事実です。家族経営であるがゆえに、内部のことはあえて言語化しない、暗黙の了解で動いている――そんな状況が、「備えるべきことが備えられないまま放置されるリスク」を生み出してしまいます。
たとえば、事業承継の準備が整わないまま突然の経営者交代が起きたり、災害や感染症などの外的要因によって取引や供給体制が一変したりするケースは、決して珍しいことではありません。また、長年蓄積されてきた人間関係が、相続や経営判断をきっかけに崩れ、対立や混乱に発展することもあります。
このように、「まさか」の出来事は、どれほど堅実な企業であっても例外ではありません。しかも、ファミリービジネスにおける経営リスクは、業績や契約のような外部指標では見えにくく、内部に潜んでいることが多いため、表面化したときにはすでに手遅れ、という事態にもなりかねません。
だからこそ、ファミリービジネスにとってのリスクマネジメントは、単なる「不安への備え」ではなく、変化に対応し、企業を次の世代につなぐための“土台”を整える戦略的な経営課題なのです。
ファミリービジネスに多い経営リスクとその特徴・対策
ファミリービジネスは、長期視点での経営や地域・顧客との強固な関係、意思決定のスピードといった独自の強みを持つ反面、「人」や「関係性」に起因する脆弱性が内在しているケースが少なくありません。こうしたリスクは、目に見えにくく、組織の中で“暗黙の了解”として長年放置されていることも多いため、いざという時に表面化すると、企業の根幹を揺るがす重大な問題に発展しがちです。
以下に、ファミリービジネスに特有の代表的な経営リスクを整理してみましょう。
経営者依存リスク
経営者の長年の経験やカリスマ性、取引先との強い関係に業務全体が依存しているケースは、ファミリービジネスではよく見られます。こうした状況では、意思決定が属人的になり、他の幹部や家族が詳細を把握していないことも多くあります。
その結果、経営者が急逝したり病気で離脱したりした場合、意思決定の停滞、顧客・取引先との信頼関係の失墜などが一気に起こる恐れがあります。日常業務が止まり、金融機関や従業員が混乱に陥るといった事例も現実に起きています。
相続・資産分散リスク
事前の相続設計や議論がなされていない場合、株式が複数の相続人に分散してしまうことがあります。これにより、経営権が不安定になり、意思決定にブレが生じるだけでなく、経営に関与していない株主が配当や売却益を優先して経営判断に介入してくることもあります。
株主間での利害対立がエスカレートすれば、企業の長期的な方向性が不透明になり、社内の士気や対外的な信頼に悪影響を及ぼす可能性があります。
家族間の対立リスク
後継者選定や経営方針、役員構成をめぐって、兄弟姉妹・親戚間で対立が起こることはファミリービジネスの宿命ともいえます。一度感情的な対立が顕在化すると、それは単なる意見の食い違いでは済まなくなるのが家族経営の難しいところです。
派閥の形成や意思決定の分裂が起きれば、従業員は誰の指示に従えばよいのか分からず、現場が混乱し、離職や士気の低下を招く事態にもなりかねません。
情報・ノウハウの属人化リスク
長年の取引や事業のノウハウ、業務判断の基準などが、経営者や古参社員の“頭の中”にしか存在していない。これもファミリービジネスにおいてよく見られる構造です。
このような状態では、業務の引き継ぎや多部署での対応が困難になり、少数の個人に業務が集中してしまうという問題が起きます。承継の際に知識の空白が生まれたり、思わぬミスや不正の温床になることもあるため、属人性から“組織知”への転換が急務です。
外部環境リスク(自然災害・感染症・サプライチェーンの混乱など)
2020年以降のパンデミックや、急激な原材料価格の変動、気候災害の頻発など、外的なリスクは年々増加しています。特に中小規模のファミリービジネスでは、一度の危機で資金繰りが悪化し、事業継続が困難になるケースも珍しくありません。
備蓄・サプライチェーンの多元化・BCP(事業継続計画)の整備といった対応策を講じておくことが、企業の“しなやかさ”と“打たれ強さ”を支える要素となります。

これらのリスクは、今この瞬間に問題として表れるものではないかもしれません。日々の業務が順調に回っているときほど、つい見落としてしまいがちですが、じわじわと進行している“見えにくいほころび”として、企業の足元に影を落としている可能性があります。
だからこそ、「気づいたときにはもう遅い」とならないように、少し立ち止まって見直してみる姿勢が、これからの経営には欠かせません。大きなトラブルを防ぐための第一歩として、今できる準備から始めていくことが大切です。
経営の属人化を防ぐ「見える化」対策とその実践ポイント
ファミリービジネスでは、創業者や現経営者の判断力・人脈・経験といった「個の力」が、企業の成長や存続を支える大きな強みとなってきました。その一方で、あらゆる意思決定がその個人に集中している場合、経営の属人化というリスクを内包している点には注意が必要です。
- 資金繰りや銀行対応の判断を、経営者だけが把握している
- 長年の取引先との信頼関係が、経営者個人の信用に依存している
- 社内ルールや事業の進め方が形式化されず、口頭や慣習で引き継がれている
- 幹部や後継者が重要な意思決定の場に関与できず、経営の全体像を理解できていない
このような体制のまま経営者が病気や事故などで急に不在になると、事業の流れが止まり、取引や社内業務に混乱が生じる恐れがあります。場合によっては、企業の信用低下や事業継続の危機に直結する可能性も否定できません。
対策1:意思決定と情報の「見える化」
まず最初に取り組みたいのが、属人化している情報やプロセスを「見える形にして残す」という作業です。経営判断がどのように行われているか、どんな情報が根拠になっているかを明文化し、組織全体で共有できる仕組みを整えましょう。
- 契約書・財務データ・人事情報など、重要情報を一元管理できるシステムを導入する
- 各業務の進行フローや判断基準をマニュアル化し、属人的な手順を誰でも再現できる状態にする
- 経営会議や意思決定のプロセスを議事録にまとめ、関係者が振り返れるようにする
特にベテラン経営者が「感覚で判断している」ような部分こそ、時間をかけて形式化する必要があります。再現可能性を高めることは、後継者や幹部の育成にも直結します。
対策2:幹部や後継者を巻き込んだ“経営の共創”
属人化から脱却するためには、「経営は一人ではなく、複数で担うもの」という体制づくりへの転換が欠かせません。知識や判断力の継承は、共に実務を経験するなかでこそ実現します。
- 定期的に経営会議を開催し、後継者や幹部が経営判断に関わる機会を設ける
- 経営者の代理として、小規模な案件の意思決定を後継者に任せ、経験を積ませる
- 社外の専門家や士業とともに幹部を交えたブレストやレビューを行い、視点を共有する
こうしたプロセスを通じて、単なる「権限の委譲」ではなく、“経営の知の継承”が進みます。これは、見えない資産である「判断の感覚」や「意思決定の基準」を共有化する取り組みでもあります。
経営の属人化が続くと、事業は一見順調に見えていても、成長の限界や組織の脆弱さが徐々に表面化していきます。経営の要となる人物が不在になるだけで、意思決定が滞り、社員が動けなくなってしまう――そんなリスクは、将来の発展を阻む大きな障壁となります。
だからこそ今こそ大切なのは、「特定の人に頼らなくても回る仕組み」を意識的につくっていくことです。仕組みによって支えられる組織は、環境の変化や突発的な出来事にも揺るがず、自立的に判断し行動できる力を備えることができます。
“見える経営”とは、経営の透明性を高めるだけでなく、組織全体の対応力や柔軟性を引き出すための実践的な戦略です。それは、いざというときの「守り」になるだけでなく、将来の挑戦に備える「攻め」の土台にもなるのです。
ファミリービジネスに潜む「家族内対立リスク」への対応法
ファミリービジネスにおいて、最も根深く、かつ表面化しづらいリスクの一つが「家族間の対立」です。血縁による強い絆がある一方で、その“近さ”ゆえに起こる感情的なしがらみや、遠慮・対立が複雑に絡み合います。
本音が言えない、感情をぶつけられない、逆に遠慮なく言いすぎてしまう――。こうした状況が積み重なると、経営上の問題が家族の感情問題にすり替わり、冷静な判断や対話ができなくなってしまうことがあります。
ファミリー内対立と経営への影響
とくに以下のような事態は、企業の意思決定を鈍らせたり、承継プロセスを混乱させたりと、事業の継続に深刻な影響を与える恐れがあります。
- 継がせたい親と、継ぎたくない子どもの意志のすれ違い
- 兄弟姉妹間の「役割の不公平感」や「貢献度に対する不満」
- 経営に関与しない親族からの意見、干渉、利益要求
このようなリスクに向き合うためには、単なる親子や兄弟の会話では限界があります。あらかじめ仕組みとして“対話の場”や“合意形成の手段”を用意しておくことが不可欠です。
解決のために有効なアプローチ
ファミリーガバナンス(ファミリー会議・合意文書)を整備する
家族間のルールや役割を明文化し、定期的に話し合いの場を持つことで、感情のすれ違いや誤解を未然に防ぐことができます。
承継計画をオープンに共有し、関係者の合意を形成しておく
「誰がいつ何を引き継ぐのか」「どう分けるのか」を明示することで、不安や憶測が広がるのを防ぎます。
外部ファシリテーター(顧問・士業)を交えて、感情を整理する
家族だけでは整理しづらい感情や利害のもつれも、第三者が間に入ることで、冷静で建設的な対話が可能になります。
ファミリービジネスにおける感情的なトラブルは、数字に表れない“見えないリスク”であり、時として事業の根幹を揺るがす厄介な火種になります。だからこそ、問題が起きてから対処するのではなく、「問題が起きないように設計する」ことが最も有効なリスク対策なのです。
日常の中で、家族だからこそできる対話をどう積み重ねていくか――それが、事業の未来を守る第一歩となります。
ファミリービジネスのためのBCP(事業継続計画)とは?整備の基本と進め方
ファミリービジネスにこそ必要な事業継続計画とは
企業が不測の事態に備えるために欠かせないのが、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の整備です。これは、大規模災害や感染症の流行、サプライチェーンの寸断、経営者の突然の不在といった“突発的な危機”に直面した際、企業が「いかに事業を止めずに維持・再開できるか」を具体的に定めた計画です。
中小企業やファミリービジネスでは、「大企業の話」として後回しにされがちですが、人的・資金的リソースが限られるからこそ、最小限の損害で事業を守るための事前準備が不可欠です。完璧な計画を最初から用意する必要はありません。まずは自社に合った現実的なBCPの骨格をつくり、継続的に見直していくことが大切です。形にすることから始める――その小さな一歩が、非常時には“生命線”となります。
BCPに盛り込むべき基本要素
緊急時の代行体制の明記(誰が何を引き継ぐか)
経営者やキーパーソンが不在となった場合、誰がどの業務を代行するのか、役割分担を明確にしておくことが肝心です。
事業継続に必要な資源(人・物・金・情報)のリストアップ
どの社員・設備・取引先・在庫・情報システムが事業の継続に不可欠かを整理しておくことで、優先順位の高い対応が可能になります。
非常時の連絡体制・マニュアルの整備(社内・外部向け)
社員や取引先に迅速に情報を共有するための連絡網、災害時対応のフローや対応方針を定めておきます。
資金繰り悪化時の対処方法や金融機関との関係整理
緊急時には売上が減少し、キャッシュフローに問題が生じやすくなります。融資枠の確認や相談先の明確化も含めて、あらかじめ準備しておくことが重要です。
BCPは、「一度作れば終わり」の計画ではありません。環境の変化や人員の入れ替わりに応じて、定期的に見直し、訓練し、アップデートすることが不可欠です。最低でも年に一度はBCPの内容を確認し、関係者と情報を共有し、実際に動けるかをチェックする「シミュレーション訓練」などを実施するとよいでしょう。
不測の事態は、いつ、どのようなかたちで訪れるかわかりません。しかし、備えていた企業とそうでない企業とでは、対応スピードと回復力に大きな差が生まれます。BCPの整備は、経営の安全装置であると同時に、従業員や取引先からの信頼を高める手段でもあるのです。
▶ 参考:
・事業継続力強化計画(中小企業庁HP)
・中小企業BCP策定運用指針(中小企業庁HP)
・中小企業必見!「事業継続力強化計画」認定制度の徹底解説と実践ガイド(FBMオフィス)
次のステップ:今すぐできる!ファミリービジネスのリスク管理セルフチェックリスト
ファミリービジネスにおけるリスク管理は、単に「将来の危機を予測する」ことが目的ではありません。むしろ重要なのは、予測できない事態が起きたときに、どれだけ速やかに対応し、事業を維持できるかをあらかじめ設計しておくことです。リスク管理とは、経営の“柔軟性”と“回復力”を高めるための基盤づくりともいえます。
以下のような視点から、自社の現状を点検し、どこにリスクの芽があるのか、今何を整えておくべきかを確認してみましょう。
- ✅ 経営者が突然不在になったときの「代行体制」は整備されているか?
意思決定の権限や日常業務の継続に支障が出ないよう、誰が何を引き継ぐかを明確にしておく必要があります。 - ✅ 株式や事業資産の管理状況は、承継先が明確になっているか?
「後で考える」では遅すぎます。相続時のトラブルや分散リスクを防ぐには、早期からの方針共有と対策が不可欠です。 - ✅ 家族内での役割と関係性は、目に見える形で共有・合意されているか?
暗黙の了解や思い込みは、後々の対立や誤解を生む要因になります。立場と責任を明文化し、話し合いの機会を持つことが大切です。 - ✅ 非常時の業務継続体制や、情報共有の仕組みは整っているか?
災害・感染症・サプライチェーンの混乱など、さまざまな外的リ스크に対応するには、簡単でもよいのでBCPの骨格をつくっておきましょう。
これらはすべて、「明日いきなり起きてもおかしくないこと」ばかりです。そして、その備えは一朝一夕ではできません。だからこそ、“今できること”を少しずつ積み重ねることが、未来の安心につながります。
事業という“生命線”を守るために、まずは気づくこと、そして行動することから始めましょう。
次回予告:ファミリービジネスの未来を育てる!10年先を見据えた成長戦略
ファミリービジネスが持続可能なかたちで未来へと歩みを進めるためには、資産や経営権の承継にとどまらず、「人が育つ土壌」をいかにつくるかが重要な鍵になります。組織が生き続けるには、変化に対応できる力と、共に未来を育てる視点が欠かせません。
- 持続可能な成長とは、単なる事業拡大ではなく、どんな状態を指すのか?
- 家族経営ならではの価値と強みを、どう未来に活かせばよいのか?
- バトンを渡すだけでなく、“共に育つ”組織とは、どう築くのか?
次回はいよいよシリーズ最終回。テーマは、
「ファミリービジネスの未来を育てる:10年先を見据えた成長戦略」です。
▶ 次回はこちら:
「ファミリービジネスの未来を育てる:10年先を見据えた成長戦略」
これまでの連載の学びを総括し、未来志向で歩み出すための実践的ヒントをお届けします。どうぞお楽しみに。
ファミリービジネスマネジメントオフィス
シニア・プライベートバンカー
平野 泰嗣
ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMオフィス)からのご案内:
「うちの会社にも当てはまるかも…」そう感じた方へ。
ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)では、家族と企業の未来を大切にした、あなただけの経営支援を行っています。
小さな疑問から、複雑な承継の悩みまで、お気軽にご相談ください。
経験豊富なアドバイザーが、じっくりお話をうかがいます。
👉 お問合せ・初回相談のご予約はこちら